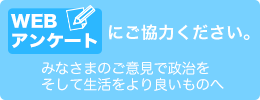議会レポート
本会議
平成30年6月20日 平成30年第 4回 沖縄県議会(定例会)
2018年08月22日
○赤嶺 昇 おはようございます。
きのうはワールドカップで日本が勝って大変喜んでおります。実は、私ブラジル生まれで11歳までブラジルにいたものですから、このワールドカップのときのブラジルの騒ぎというのは大変なもので、みんな仕事しないんじゃないかなと思うぐらいサッカーに夢中になっている。ところが今日本も近年は野球も人気なんですけれども、それを上回るぐらいのサッカー人気で、きのうの勝利は厳しいと言われている中でよくも勝ってくれたなと今日本中が喜んでいるんじゃないかなと思っております。この調子でぜひとも決勝進出、決勝トーナメントに進んでいただきたいなと思っております。
それでは、会派おきなわを代表して質問を行います。
1番、知事の政治姿勢について。
(1)、辺野古新基地建設阻止への取り組みについて伺います。
(2)、県民投票について所見を伺います。
(3)、北朝鮮情勢について所見を伺います。
(4)、北朝鮮の脅威について所見を伺います。
(5)、朝鮮南北首脳会談について所見を伺います。
(6)、米朝首脳会談について所見を伺います。
(7)、北朝鮮情勢と本県の米軍基地の整理縮小について伺います。
(8)、モノレール延長事業の進捗状況とさらなる延伸計画について伺います。
(9)、鉄軌道、LRT等の導入について伺います。
(10)、一国二制度に対する考え方について伺います。
2番、翁長県政の4年間の主な経済政策の実績について。
(1)、県内生産について。
(2)、1人当たり県民所得について。
(3)、入域観光客数について。
(4)、観光収入について。
(5)、クルーズ船の実績と見込みについて。
(6)、アジア各地との間の直行便数について。
(7)、那覇空港の国際貨物取扱量について。
(8)、完全失業率について。
(9)、有効求人倍率について。
(10)、沖縄へ立地した情報通信関連企業の雇用者数について。
3番、知事公約の達成状況について伺います。
4番、教育行政について。
(1)、小・中・高のいじめの課題について。
(2)、小・中・高の不登校の課題について。
5番、福祉行政について。
(1)、待機児童の課題について。
(2)、学童保育の課題について。
(3)、児童虐待の課題について。
6番、医療行政について。
(1)、県立北部病院と北部地区医師会病院の統合の課題について。
(2)、県立病院の課題について。
7番、土木建築行政について。
(1)、地元企業優先発注の状況について。
(2)、技術者不足の課題について。
(3)、県発注工事の不調・不落について。
(4)、入札制度の課題について。
8番、文化観光スポーツ行政について。
(1)、観光客レンタカーの課題について。
(2)、東京オリンピック・パラリンピックへの対応について。
9番、商工労働行政について。
(1)、駐留軍離職者対策センターの課題について。
(2)、商工労働行政の課題について。
10番、農林水産行政について。
(1)、農林行政の課題について。
(2)、水産行政の課題について。
11番、公安行政について。
(1)、観光客増に伴う公安行政の課題について。
(2)、違法薬物の課題について。
12、那覇空港について。
(1)、那覇空港の課題について。
(2)、那覇空港の民営化について。
13、MICEについて。
(1)、進捗状況と見通しについて伺います。
○議長(新里米吉) 翁長知事。
〔知事 翁長雄志君登壇〕
○知事(翁長雄志) ハイサイ グスーヨー チューウガナビラ。
赤嶺昇議員の代表質問にお答えをいたします。
知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の1の(2)、県民投票についてお答えをいたします。
これまでに他の地方公共団体で実施された住民投票は、その施策決定に大きな影響を与えてきたものと認識をしております。また、県民投票については、県民が主体となって議論がなされることが重要であると考えております。政府が辺野古新基地建設を強行する中で、米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票が実施されれば、県民一人一人が改めてその意思を明確に示すことができるため、今回の県民投票は意義があるものと考えております。
次に、翁長県政の4年間の主な経済政策の実績についてに関する御質問の中の、入域観光客数と観光収入の実績についてお答えをいたします。2の(3)、2の(4)は関連しますので一括してお答えをいたします。
平成29年度の入域観光客数は957万9900人で、平成25年度と比べて299万9600人、45.6%の増となっております。また、平成28年度の観光収入は6602億9400万円となり、平成25年度と比べ2124億2600万円、47.4%の増となっており、順調に推移しております。
次に、完全失業率、有効求人倍率についてお答えをいたします。2の(8)と2の(9)は関連いたしますので一括してお答えをいたします。
沖縄県の雇用情勢については、好調な観光需要の増加等による県内景気の拡大に加え、産業振興や企業誘致などに取り組んだ結果、年平均の完全失業率は平成25年の5.7%から平成29年の3.8%、有効求人倍率は平成25年の0.53倍から平成29年の1.11倍と着実に改善をしております。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁をさせていただきます。
○議長(新里米吉) 知事公室長。
〔知事公室長 池田竹州君登壇〕
○知事公室長(池田竹州) 1、知事の政治姿勢についての(1)、辺野古新基地建設阻止の方法についてお答えします。
県としては、埋立承認に付した留意事項に基づく事前協議が調った後でなければ工事への着手は認められないことから、直ちに工事を停止し、事前協議を行うよう求めているところであります。撤回については、埋立承認に付した留意事項に基づく事前協議やサンゴ類の移植を初めとした環境保全措置などについて、沖縄防衛局への行政指導等を行っていることも踏まえ、日々の国の動き等全体的な流れを勘案しながら、あらゆる状況を想定して検討し、県としてしっかりと対応してまいりたいと考えております。
同じく1の(3)、1の(4)及び1の(7)、北朝鮮情勢と在沖米軍基地への影響についての御質問は関連しますので、恐縮ですが一括してお答えします。
平成29年版防衛白書によると、北朝鮮の核兵器・弾道ミサイルの開発や運用能力の向上は、新たな段階の脅威となっているとしております。一方で、4月と5月に南北首脳会談が開催され、去る6月12日には米朝首脳会談が開催されるなど、緊張緩和に向けた動きが見られるところです。在沖米軍基地への影響については、現段階では明らかではありませんが、沖縄県としては、今後の両国の具体的な協議等が進み、米軍基地の整理縮小等、沖縄の過重な基地負担の軽減につながることを期待しております。
以上でございます。
○議長(新里米吉) 子ども生活福祉部長。
〔子ども生活福祉部長 大城玲子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長(大城玲子) 1、知事の政治姿勢についての御質問の中の(5)と(6)、南北首脳会談及び米朝首脳会談についてお答えいたします。1の(5)と1の(6)は関連いたしますので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
県は、人類を破滅に導く全ての核兵器の製造・実験等に反対し、あらゆる国の核実験に対して抗議するため、平成7年に非核・平和沖縄県宣言を行い、あらゆる国による核兵器の実験に対してその都度抗議を行っております。悲惨な地上戦を体験した沖縄県としては、平和を脅かす核兵器の廃絶に向けて、朝鮮半島の完全非核化を確認・約束した板門店宣言及び米朝首脳会談における合意文書が、東アジアの平和構築につながることを期待するものであります。
次に5、福祉行政についての(1)、待機児童解消の課題についてお答えいたします。
本県における待機児童数は、平成30年4月1日時点の速報値によると1884人となっており、前年に比べ363人の減少となっております。待機児童の解消を図るための課題としては、保育ニーズの高まりによる保育所等の受け皿整備、保育士の確保と処遇改善、地域別・年齢別ニーズとのミスマッチによる定員割れなどがあると認識しております。
同じく(2)、放課後児童クラブの課題についてお答えいたします。
放課後児童クラブ実施状況調査の速報値によると、平成30年5月1日現在の登録できなかった児童数は前年度と比較して88人減少しているものの、760人となっております。登録できなかった児童数が多い市町村は、沖縄市、宜野湾市、那覇市、うるま市、嘉手納町の順となっております。県は、放課後児童クラブ支援事業により、平成24年度から29年度までに公的施設活用クラブ18カ所の整備を支援したところであり、引き続き、市町村と連携し、登録できない児童の解消に取り組んでまいります。
同じく(3)、児童虐待の課題についてお答えいたします。
児童虐待につきましては、近年の虐待相談件数の増加や児童及び家庭をめぐる問題の複雑化・多様化、また、それらに対応するための児童福祉法等の改正に伴い、児童相談所の役割の重要性が増しております。このことから、児童相談所の体制の充実や市町村の相談体制の強化等が課題であると考えており、県としても、引き続きこれらの解決に向けて取り組んでまいります。
以上でございます。
○議長(新里米吉) 土木建築部長。
〔土木建築部長 上原国定君登壇〕
○土木建築部長(上原国定) 1、知事の政治姿勢についての御質問の中の(8)のア、モノレール延長事業の進捗状況についてお答えいたします。
沖縄都市モノレール延長整備事業については、平成29年度末の事業費ベースで、約79%の進捗となっております。ことし8月末までに延長区間全ての軌道桁が連結する見込みであり、今後は自由通路工事などを進めてまいります。また、沖縄都市モノレール株式会社においては、電力設備等のインフラ外工事を進めており、順調に進めば平成31年1月から車両走行によるシステム総合試験を開始する予定とのことであります。延長区間の開業につきましては、平成31年夏ごろを予定しております。
7、土木建築行政についての御質問の中の(1)、地元企業優先発注の状況についてお答えいたします。
土木建築部発注工事において、平成29年度は発注件数481件、約351億6000万円のうち地元業者は468件、約327億8000万円を受注しており、地元業者の受注率は件数で95.9%、金額で93.2%となっております。
同じく7の(2)、技術者不足の課題についてお答えいたします。
沖縄労働局によると、平成30年3月の県内における建築・土木・測量技術者の新規求人倍率は3.46倍となっており、人手不足が生じていると思われます。県は、技術者不足の対策として、技術者の兼任要件の緩和や余裕期間の設定など、配置技術者の要件を緩和し、また、社会保険料個人負担分の適正加算、週休2日工事の試行など、労働環境改善や生産性向上などに取り組んでおります。さらに、建設現場体験親子バスツアーやおきなわ建設フェスタへの出展、建設業に特化した合同企業説明会開催への協力など、建設業界の魅力発進にも取り組んでいるところであります。
同じく7の(3)、県発注工事の不調・不落についてお答えいたします。
土木建築部発注工事における入札不調・不落の状況について、平成27年度開札件数833件のうち、不調・不落が187件で全体の22%、平成28年度開札件数835件のうち、不調・不落が172件で全体の21%、平成29年度開札件数605件のうち、不調・不落が124件で全体の20%となっております。
同じく7の(4)、入札制度の課題についてお答えいたします。
土木建築部が発注する工事における入札制度の課題としては、不調・不落発生率がここ数年20%台で推移しており、配置技術者の不足等がその要因と考えております。その対策として、主任技術者等の兼任要件の緩和や専任で配置を要しない余裕期間の設定など、入札要件の緩和を講じているところであります。今後も引き続き課題の改善に取り組んでまいります。
以上でございます。
○議長(新里米吉) 企画部長。
〔企画部長 川満誠一君登壇〕
○企画部長(川満誠一) 1、知事の政治姿勢についての中の(8)のイ、モノレールの延伸計画についての御質問にお答えいたします。
本県における交通政策の基本方向等を示した沖縄県総合交通体系基本計画においては、中南部圏域における陸上交通の課題として、公共交通の利便性向上による適正な交通機関分担の実現、観光需要の増加への対応と観光客の受け入れ体制の整備などを挙げ、各施策を実施してきたところであります。しかし、県民の自動車保有台数の増加や入域観光客数の急激な増加等、陸上交通を取り巻く状況は大きく変化しており、今後、さらなる交通渋滞等の発生も予想されます。このため、県としては、これら課題に対応すべく、多様な交通手段について幅広く検討を行う必要があると考えており、都市交通であるゆいレールの延伸の可能性等についても今年度から調査してまいりたいと考えております。
同じく1の(9)、鉄軌道、LRT等の導入についての御質問にお答えいたします。
県では、平成26年度から沖縄鉄軌道の計画案づくりに取り組み、ことし5月に沖縄鉄軌道の構想段階における計画書を策定し、県としての考えを取りまとめました。県としては、今後、鉄軌道導入に向けた機運醸成を図るとともに、公設民営型の上下分離方式を可能とする特例制度の創設等、早期の事業化を国に働きかけてまいりたいと考えております。また、LRTを含めた将来のフィーダー交通ネットワークの構築を見据え、各地域における交通の現状と課題等を踏まえた公共交通の充実について、沖縄本島内を複数のエリアに分けた議論の場を設定する等、まちづくりの主体である市町村等との協働により検討を進めてまいります。
同じく1の(10)、一国二制度に対する考え方についてお答えいたします。
沖縄県においては、企業誘致や投資の促進等を目的として、国際物流拠点産業集積地域や経済金融活性化特別地区など特区・地域制度が設けられております。同制度においては、10年間40%の所得控除や4年間の繰り越しが可能な投資税額控除など高い控除率や控除期間が措置されており、ほかに例のない一国二制度的な内容となっております。こうした制度を最大限に活用するとともに、アジアの中心に位置する本県の地理的優位性を生かし、成長著しいアジアの活力を取り込む諸施策を展開することで我が国経済再生の牽引役となっていけるものと考えております。
次に、2の翁長県政下の県内総生産と1人当たり県民所得についてお答えいたします。2の(1)と2の(2)は関連しますので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
沖縄県の経済は、翁長知事在任中の全ての期間で拡大を続けております。また、日銀の業況判断DIも全期間でプラスとなっており、全国と比べても好調に推移しております。こうした中、平成27年度の名目県内総生産は4兆1416億円となり、平成26年度と比べて1863億円、4.7%の増加となっております。また、平成27年度の1人当たり県民所得は216万6000円となり、平成26年度と比べ7万8000円、3.7%の増加となっております。
県としては、今後も観光分野を中心に経済情勢は好調を維持すると見込んでおり、県内総生産及び1人当たり県民所得も順調に伸びていくものと考えております。
次に3の(1)、知事公約の達成状況についてお答えいたします。
知事公約については、その実現に向けて、経済発展、生活充実、平和創造の3つの視点から取り組んでいるところです。経済発展については、沖縄県アジア経済戦略構想を推進し、観光・リゾート産業や情報通信関連産業などを強化するとともに、国際物流拠点の形成に取り組んでおります。生活充実については、子供の貧困問題の解消に向けて基金を設置して取り組んでいるほか、離島地域の活性化なども積極的に推進しております。平和創造については、辺野古新基地建設に反対し、普天間飛行場の県外移設及び早期返還、危険性の除去に取り組んでおります。このような取り組みにより、平成29年度の入域観光客数は約958万人となり、5年連続で過去最高を更新しました。観光・リゾート産業の関連産業を含めた経済波及効果は1兆円を超え、情報通信関連産業の売上高は4200億円、農業産出額は1000億円を達成するなど、県経済は好調に推移しております。また、年度平均の完全失業率は、平成29年度が3.6%と改善し、有効求人倍率も復帰後初めて1倍を記録するなど、県政運営の成果は着実に上がっているものと考えております。
次に12の(1)、那覇空港の課題についての御質問にお答えいたします。
現在、那覇空港は時間帯によって過密な発着状況となっており、第2滑走路の供用開始後はさらなる航空需要の増大が見込まれることから、駐機スポットの確保や旅客ターミナルの拡張などの課題に対応していく必要があります。
県としましては、本県の県民生活や経済活動を支える重要な社会基盤である那覇空港の機能強化に向けて、関係機関や関係事業者と連携し、取り組んでまいります。
次に12の(2)、那覇空港の民営化についての御質問にお答えいたします。
国においては、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化や地域経済の活性化等に寄与することを目的に、国管理空港等の運営を民間に委託する取り組みを進めています。現在、仙台空港や高松空港において民間による運営が行われているほか、福岡空港、熊本空港、北海道内7空港で手続が進められています。
県としましては、このような他空港の状況の把握に努めるとともに、県内経済界等とも連携しながら、今後の那覇空港の運営のあり方について調査検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(新里米吉) 文化観光スポーツ部長。
〔文化観光スポーツ部長 嘉手苅孝夫君登壇〕
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 2、翁長県政の4年間の主な経済政策の実績についての御質問の中の(5)、クルーズ船の実績と見込みについてにお答えいたします。
沖縄へのクルーズ船の寄港実績については、県内港湾の全体で2013年に126回であったものが、2017年に515回まで増加しております。港湾別に2013年と2017年を比較しますと、那覇港は56回から224回へ、石垣港は65回から132回へ、平良港は1回から130回へ、中城湾港はゼロから15回へ、本部港は1回から5回へ、それぞれ大幅な増加となっております。2018年は県全体で662回の寄港が予定されており、中国クルーズ市場の成長やクルーズ受け入れ港湾の整備に伴う受け入れキャパシティーの拡大により、今後さらなる寄港の増加が期待できるものと考えております。
同じく2の(6)、アジアとの直行便数についての御質問にお答えいたします。
沖縄県とアジア各地との直行便数については、平成25年度末で週78便であったものが、平成29年度末では週210便まで増加しております。国・地域別に、平成25年度末及び平成29年度末の便数を申し上げますと、台湾からは週30便から週71便に、韓国からは週17便から週62便に、中国本土からは週13便から週35便に、香港からは週18便から週32便に、それぞれ大幅に増加しております。さらに、平成25年度末当時には直行便がなかったバンコクからは、平成29年度末で週7便、シンガポールからは週3便がそれぞれ就航しております。
次に8、文化観光スポーツ行政についての御質問の中の(1)、観光客のレンタカー利用の課題についてにお答えいたします。
国内観光客の約6割、外国人観光客の約3割がレンタカーを利用することから、那覇空港では送迎バスによる混雑などの課題が生じております。また、外国人観光客のレンタカー利用については、本国との交通ルール及び標識の違いなどの理由により、日本人と比較して事故率が高い傾向があります。
県では、昨年度、那覇空港から豊崎までの区間における路線バスの実証実験を実施し、ことし4月から民間事業者の独自運行につなげたところであります。また、沖縄県レンタカー協会においては、多言語での安全運転マニュアルを作成し、利用者へ周知を図っているところであります。
同じく8の(2)、東京オリンピック・パラリンピックへの対応についての御質問にお答えいたします。
県では、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を本県のスポーツコンベンションを飛躍的に拡大させる絶好の機会と捉え、本大会で活躍できる県出身選手の育成や聖火リレーの実施に向けた取り組み等を行っているところであります。また、事前キャンプについては、平成29年にニュージーランドの空手競技とソロモン諸島の水泳競技の誘致を実現し、現在も数カ国と新たな誘致に向けて調整しているところであります。
県としては、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、引き続きこれらの取り組みを推進してまいりたいと考えております。
次に13、MICEについての御質問の中の、大型MICE施設の進捗状況と見通しについてにお答えいたします。
県は、昨年度から、政府与党や内閣府等に対し、国が課題とする需要収支見込み及び周辺受け入れ環境整備の見通しについて合計22回の説明等を重ねてきましたが、現時点において交付決定の見通しは立っておりません。
県としては、国が指摘する課題は整理済みとの認識であり、県内経済団体や関係市町村等からも資料の精度について高い評価を得ております。今後とも、基本設計の早期の交付決定に向け、地元市町村や関係団体等と連携しながら取り組んでまいります。
以上でございます。
○議長(新里米吉) 商工労働部長。
〔商工労働部長 屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長(屋比久盛敏) 2、翁長県政の4年間の主な経済政策の実績についての(7)、那覇空港の国際貨物取扱量についてにお答えいたします。
平成29年度の国際貨物取扱量は約18万トンで、平成25年度の約16万トンと比較すると、約1万9000トンの伸びとなっており、成田、関空、羽田に次ぐ国内第4位の貨物取扱量となっております。
次、同じく2の(10)、情報通信関連産業の立地企業の雇用者数についてにお答えいたします。
県が行った情報通信関連企業へのアンケート調査によると、平成29年1月1日現在で、国内外から立地したIT関連企業数は427社、雇用者数は2万8045人となっており、平成26年1月1日時点と比較して126社、3176人の増となっております。
次に、商工労働行政についての(1)、駐留軍離職者対策センターの課題についてにお答えいたします。
同センターが現在入居している県立駐留軍従業員等健康福祉センターが老朽化しており、安全面が懸念されることから、同センターの移転先の確保が喫緊の課題となっております。
県としましては、移転先に関する情報提供等を行っているところです。
同じく9の(2)、商工労働行政の課題についてにお答えいたします。
商工労働部のこれまでの取り組みにより、情報通信関連産業がリーディング産業に成長するとともに、完全失業率が大幅に改善するなど一定の成果が出ております。今後のさらなる産業振興に向けた課題としては、情報通信関連産業の高度化・多様化の促進や人手不足への対応、雇用の質の改善などがあると認識しております。
以上でございます。
○議長(新里米吉) 教育長。
〔教育長 平敷昭人君登壇〕
○教育長(平敷昭人) 4の教育行政についての御質問で、小・中・高のいじめ、不登校の課題についてお答えいたします。4の(1)と4の(2)は関連いたしますので、恐縮ですが一括してお答えをさせていただきます。
文部科学省の調査によりますと、平成28年度本県の公立学校におけるいじめの認知件数は、小学校1万513件、中学校961件、高等学校173件、特別支援学校8件の合計で1万1655件となっており、前年度比9438件の増となっております。また、不登校については小学校686人、中学校1681人、高等学校1455人の合計で3822人となっており、前年度比363人の増となっております。
県教育委員会では、沖縄県いじめ防止基本方針などの活用を通して、いじめ防止や不登校対策の取り組みが効果的に行えるよう支援するとともに、生徒指導体制の充実に努めてまいります。
以上でございます。
○議長(新里米吉) 保健医療部長。
〔保健医療部長 砂川 靖君登壇〕
○保健医療部長(砂川 靖) それでは、6の医療行政についての御質問の中の(1)、北部基幹病院についての御質問にお答えします。
県立北部病院と北部地区医師会病院の統合に際しましては、医師会病院が保有する資産及び負債の取り扱い、職員の身分取り扱い、北部基幹病院の機能、北部12市町村の協力のあり方、さらに第3回協議会で北部地区医師会病院等から提案のありました経営形態などの課題があると考えており、これらの課題について、関係者間で合意形成を図ることが最も重要な課題であると認識しております。
以上でございます。
○議長(新里米吉) 病院事業局長。
〔病院事業局長 我那覇 仁君登壇〕
○病院事業局長(我那覇 仁) 6、医療行政についての中の(2)、県立病院の課題についての御質問にお答えします。
県立病院は、各地域の中核病院として、救急医療、小児・周産期医療、高度・特殊医療、離島・僻地医療等を担っております。現在、診療科偏在や地域偏在により医師が不足していると全国的に言われている中で、病院事業局においても医師の確保が課題となっております。また、経営面では、消費税率の改正による控除対象外消費税の増や法定福利費の算定方法の変更による費用の増などの外的要因により、平成27年度から収支が悪化しております。平成29年度も時間外勤務手当の支給基準の見直し等により厳しい決算になることが見込まれるなど、収支の改善が課題になっております。
病院事業局においては、引き続き、保健医療部等と連携を図り、医師の確保及び経営の改善に向けて取り組んでまいります。
以上でございます。
○議長(新里米吉) 農林水産部長。
〔農林水産部長 島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長(島尻勝広) 10、農林水産行政についての御質問の中の(1)、農林行政の課題についてお答えいたします。
本県の農業を取り巻く環境は、農業従事者の減少や高齢化、台風や干ばつによる農作物被害、農業用水源の確保やかんがい施設の整備など、多くの課題を抱えております。そのため県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき、1、おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化、2、担い手の育成・確保及び経営安定対策等の強化、3、亜熱帯・島嶼性に適合した基盤整備など7つの基本施策に取り組んでおります。
県としましては、引き続き、持続的農林水産業とフロンティア型農林水産業の振興を図ってまいります。
同じく(2)、水産行政の課題についてお答えいたします。
本県の水産業を取り巻く環境は、魚価の低迷、資源の減少、外国漁船との漁場の競合、高齢化による漁業従事者の減少や漁業環境整備など、多くの課題を抱えております。そのため、県としましては、平成29年に策定した沖縄県水産業振興計画に基づき、1、水産物の生産供給体制の強化や販路拡大、2、沖合漁場の安全操業確保、3、担い手の確保・育成、4、水産業の基盤整備などの各施策に取り組み、水産業の振興を図ってまいります。
以上でございます。
○議長(新里米吉) 警察本部長。
〔警察本部長 筒井洋樹君登壇〕
○警察本部長(筒井洋樹) 11、公安行政についての御質問のうち(1)、観光客増に伴う公安行政の課題についてお答えをいたします。
良好な治安は、社会経済の発展の礎であり、県民が安心して暮らすことのできる社会の実現のためにも、また、当県が観光立県として一層の発展を遂げるためにも犯罪の起きにくい、安全で安心な沖縄県の実現は重要な課題であります。県内の犯罪情勢につきましては、平成14年に刑法犯認知件数が2万5641件と復帰後最多を記録したこと等踏まえ、平成16年4月にちゅらうちなー安全なまちづくり条例が施行され、県、教育庁、県警察、県民、地域社会が一体となり、県民総ぐるみによるちゅらさん運動などの犯罪抑止活動に取り組んだ結果、刑法犯認知件数は15年連続で減少し、平成29年中はピーク時の約3分の1の8047件となっております。良好な治安の確保は、ひとり警察のみによって達成できるものではありません。
県警察といたしましては、今後とも関係機関・団体や地域社会と連携し、犯罪の起きにくい安全で安心な沖縄県の実現のため、各種取り組みを推進してまいる所存であります。
次に同じく11、公安行政についての御質問のうち(2)、違法薬物の課題についてお答えをいたします。
県内における過去5年間の違法薬物事犯検挙人員は、その総数と大部分を占める覚醒剤と大麻について見てみますと、平成25年は100人でうち覚醒剤は72人、大麻は24人、平成26年は総数125人でうち覚醒剤は61人、大麻は41人、平成27年は総数167人で覚醒剤が80人、大麻が57人、平成28年は総数が175人で覚醒剤が75人、大麻が79人、平成29年は総数188人で覚醒剤が112人、大麻が67人となっております。覚醒剤については、横ばいないし増加、大麻については増加傾向にございます。
県警察といたしましては、末端乱用者の徹底検挙による需要の根絶、暴力団等の密売組織の徹底した取り締まりによる供給元の遮断、税関等関係機関と連携した水際対策、薬物乱用防止教室等による若者を初めとする県民に対する広報啓発活動等の薬物事犯総合対策に取り組んでいるところであります。
特に、入域観光客の増加に伴いまして、密輸入事犯の対策は重要な課題と考えており、一昨年には大型クルーズ船利用客による覚醒剤密輸入事件や、ヨットを利用した覚醒剤600キロの密輸入事件等を摘発しておりますが、今後とも同種事案の発生が懸念されることから、他府県警察や税関、海上保安庁、麻薬取締支所など関係機関と緊密に連携をし、水際対策を強化してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(新里米吉) 赤嶺 昇君。
〔赤嶺 昇君登壇〕
○赤嶺 昇 まず知事の政治姿勢の(1)番の辺野古新基地建設阻止への取り組みについてなんですけれども、6月16日の朝日新聞の記事で、同新聞社の航空写真で沖縄防衛局が名護市辺野古の新基地建設を進める埋立予定海域内で、同局が未確認としている2つの大型サンゴが存在しているという可能性が判明しました。日本自然保護協会によると、航空写真によって生きているサンゴがいる可能性が格段に高いということがわかったと。こんな大きなものを見逃すほど国の調査がずさんだと指摘しております。この件について県の見解と対応をお聞かせください。
それから、県として防衛局への調査のやり直しと、県による米軍に立入調査を求めるべきではないかということで、これはできたら謝花副知事のほうから答弁をお願いします。
それから北朝鮮についてなんですけれども、今回、去年と打って変わってかなり情勢が変わってきている中で、今度日本政府も日朝会談に向けて前向きということは、これは我が沖縄県にとっても大変大事なことだと思っております。拉致問題の解決も大事なことでもありますし、ここに来て日朝会談が成功し願わくば日本と北朝鮮の国交正常化に向かっていくということは、我々日本を含め沖縄の平和につながるものじゃないかなと思っております。
そこで北朝鮮の非核化と平和に向けた行動と在沖米軍基地の整理縮小に関連していくことは、大変大事なことだと思いますが、知事の見解をお聞かせください。
続いて、翁長県政のいわゆる経済政策の答弁をいただきましたが、大変実績が大きいなと率直に感じております。やはりこの4年間、基地問題でかなり忙殺されてきている中において、経済政策を着実に進めてきたことは大変私も、点高く評価しております。いろいろと指標がどんどん上がっていく中において、特にクルーズ船の見込みについてさっき答弁あったんですけれども、平成24年が125回ですよね。30年が662回ということは約6倍くらいクルーズ見込みがふえたということは、これはすごい実績じゃないのかなと。しかも那覇港のみならず中城、本部、宮古、八重山含め今後さらなる離島もクルーズ船寄港に向けても、離島を輝かせるような施策もこれからもしっかりと取り組んでいただきたいなということを要望しておきたいと思っております。
それから教育問題についてなんですけれども、小・中・高のいじめ問題で特に気になることは、平成27年から28年にかけて小学校のいじめが7倍以上伸びております。これ恐らく小さなことでもいじめをしっかりとチェックしていこうということだと思うんですけれども、数が伸びたからといって必ずしも悪いとは言いません。いじめ問題がかなり今深刻化している中において、子供たちによる自殺等も出ている中において、全体的に意識を上げることは大変いいことだと思っていますので、引き続き県教育委員会としてもこのいじめ問題についてしっかりと学校現場も含めてきめ細かく対応していただきたいということを要望しておきたいと思っています。
それから小中学校の不登校についてなんですが、27年から28年にかけて小学校の不登校もちょっとふえているんですね。このあたりの対策をどう考えているか。中学校とかわって高校もふえておりますので、この2点、どう対応するかということについてお聞かせください。
福祉行政についてなんですけれども、皆さんから1884名の待機児童がいるということを答弁いただいているんですけれども、一方で潜在的待機児童の問題があります。例えば浦添でいうと、ホームページで出ている待機児童は64名なんです。ところが電話して、何名今待機で入れないかというと、一番直近でおととい電話したら277名が待機児童なんです。潜在的待機児童がいるということは、そこにも注目しておかないと待機児童のカウントの部分を皆さんがチェックしてもらわないと、第2、第3希望を書かないとか、どこでもいいということを書かなければ待機児童からはじくということは、結果的に待機児童の解消に影響するんじゃないかなと私は思っていますので、そこでお聞きします。
潜在的待機児童の数と、それから今国に公表している待機児童の数と潜在的待機児童の合計数をお聞かせください。この合計数を合わせた数に対応していかなければ待機児童の解消につながらないんじゃないかなと思いますけれども、この件についてもお聞かせください。
それから保育士不足についてなんですけれども、さまざまな対策を講じておりますけれども、資格を持ちながら保育士をやっていない保育士が約1万人いるということで、この件についてもしっかりと潜在的な保育士の対策を処遇の面も含めて対応していただいて、これは要望にとどめたいと思っております。
それから児童虐待についてなんですけれども、最近また本当に幼い子供が命を落としたということで大変痛ましいことなんですけれども、沖縄県でも起きたりしておりますので、気になるのが児童相談所の体制なんですね。最近当局とやりとりをしたら、1人当たりのケースというのが大体40件ということだったので、以前は100件ぐらいケースを持っていたりして職員が大変なんです。要するにいろんなケースがあって、半分親からおどされながら仕事をしているということもあったりして、この児童相談所の職員体制についてはいま一度この件についてもしっかりと補強して職員の体制をやって、なおかつ児童虐待について――市町村も今頑張って窓口になっているんですけれども、児童虐待の未然防止も含め対応していただきたいということを要望しておきたいなと思っております。
それから県立病院なんですけれども、赤字が重なっているこの問題については、我々としてはこの県立病院というのは、本県において6県立病院は大変大事な沖縄県民の最後のとりでと言われているぐらい大きな役割を果たしておりますので、この件についても行革も大事なんですけれども、職員体制、看護師の体制もしっかりとやっていただきたいなと思っております。
最後なんですけれども、離対センターの件ですが、アスベストの問題を初め駐留軍離職者対策センターについては大変大きな役割を担っておりますので、この役割と責任について改めて担当副知事から答弁をお願いします。
以上です。